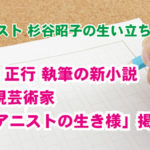前半のバロック、古典、ロマン派というクラシック音楽のクラシックらしい様式感と異なる後半最初の曲、フォーレ:ワルツ・カプリース第1番Op30。昭子の抱く霧鐘の調べと違って、エネルギッシュで自信に満ち溢れた硬質な演奏、近現代の音楽様式の違い以上の違和感を抱く。
1967年4月17日(月)日本フィルハーモニー交響楽団第139回東京定期公演 指揮・渡辺彰男。ソリスト・サンソン・フランソワという世界的名ピアニストによる生演奏、はじめて聴ける事になった昭子。自分が好きな曲を弾くのと同じように聴く事を楽しみにしていた彼女にとって、この日このときは待ちわびる思いであった。
数人のピアノレッスン生のうち、昭子がその日のうちの最初にレッスンを受けるようになったのにはこんなわけがあった。入学当初、下宿先での音事情にあわせ、昭子の家の物入り事情。
聞き分けがよく、頑張り屋の彼女は日々のピアノ練習をするにあたって学校にある いくつかの練習室の中でも状態がよいピアノを弾きたい、と早朝一番に登校していた。当然、皆の暗黙の了解事となり先生にも伝わって、井口秋子先生のレッスンではいつも最初のレッスン生になることが決まっていた。人間味のある優しさはあっても、レッスンは厳格で厳しく、ハイフィンガー奏法の指導についても徹底されていた。昭子は、うまくなっていろんな曲を弾きたい・・・。熱意があって熱心にレッスンを受け止め、ハイフィンガー奏法の習得も早く身につけることができていたのであった。が、その奏法によって発せられる音色には、今ひとつ気がかりな思いを抱いていた。それが昨夜、中村紘子のコンサートを聞き、立派なプログラムにそれを見事に弾きこなした彼女ではあったが、自分が気がかりになっていた音色について、改めて疑問を膨らませることになったことを今さらのように思い出す昭子であった。